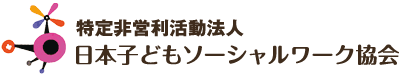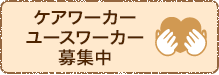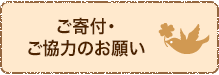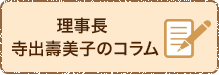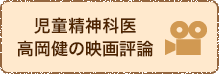プロフェッショナルな子ども3人の演技:「ふつうの子ども」
Vol.109 更新:2025年9月12日
▼イラン映画以外でも、子どもが主役の作品がありうることが実証された。評判になるのも必然だ。イラン映画と比べて差異があるとすれば、「ふつうの子ども」(呉美保監督)では小学生役の3人(嶋田鉄太・瑠璃・味元耀大)が、役柄を完全に研究して演技に反映させることができている点だ。経験豊富な嶋田や味元はもちろん、比較的キャリアが少ないらしい瑠璃もそうだ。その意味ではプロフェッショナルの演技とさえ言っていいと思う。
▼虫の好きな小学4年生の唯士(嶋田)のクラスでは、作文の発表が行われていた。そこで心愛(瑠璃)は地球温暖化をめぐり、大人を非難する作文を読み上げる。心愛に惹かれた唯士は、環境問題の本を読む心愛を探すため図書館へ出かける。「いる、いないな」と呟きながら探す唯士の姿は名演技の一例だ。
▼そこへ陽斗が加わり行動を焚きつける。3人は、チラシから切り取った文字で作成した「車を使うな」というビラを、駐車中の車に貼り付ける。ロケット花火に点火し精肉店へ発射する。牧場の柵をスパナ等で外し牛を逃がす。これらの行動の過程で描かれた、前屈みで自転車を漕ぐ心愛と、キックボードとブレイブボードで追いかける2人の場面は、理念を疑わない子どもと、理念と関係のない理由で従う子どもがうまく演じられているが、これはおそらく監督か脚本家の手腕だろう。
▼結局、3人の行動が明るみに出て、それぞれが母親とともに学校へ呼び出される。泣く陽斗と、「断れなかったんだよね」と庇う陽斗の母。環境問題を熱弁する心愛と、家庭でもよく環境問題を話し合うのかと尋ねられ「全然」と答える心愛の母。環境問題よりも心愛が好きだからやったと述べる唯士と、言葉なくハンカチを差し出す唯士の母。これら3人の母の対比自体が絵になるし、子ども3人の演技に釣り合う大人3人の演技は、これしかないなと、納得させられる。とりわけ心愛の母(瀧内公美)の少しずれたかのような、ふてぶてしさは圧巻だ。
▼本筋からは外れるが、この作品は、エコロジーをわかっていない大人たちを風刺しているようにもとれるが、エコロジー思想の珍奇さを揶揄しているようにもとれる。たぶん後者だろうと思いたいところだが、この優れたエンターテインメント作品にとってはどちらでもいい話なのだろう。だから、3人の子どもが成人に近づくにつれて、グレタ・トゥーンベリのような活動家になるのか、そうでないのかはわからないし、そういう感想そのものが野暮というものだろう。なお、この映画には、How dare you!という言葉が要所に挟みこまれている。関西弁でいう「よういうわ」「ようやるわ」というほどの意味か。
▼毎日新聞(2025年9月10日)は、「イジメや家庭環境で悩んでいるか、もしくはずっと元気いっぱいか。でも現実の子どもたちは、そんなに単純じゃない。大人の思い込みを描かない」という呉監督の言葉を紹介している。その意図は肯定的に観客へ伝わった。