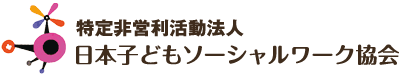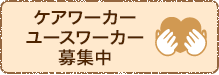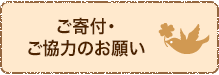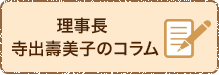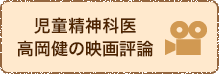この生活には戻りたくない:「小学校〜それは小さな社会〜」
Vol.103 更新:2025年3月1日
▼おおよそ誰もが、かつては小学生だったから、ドキュメンタリー映画「小学校」(山崎エマ監督)に関しては、観た人の数だけ異なった感想があるだろう。それらの中には、日本に暮らす人々が北朝鮮の一糸乱れぬ分列行進やマスゲームを見て、ああはなりたくないと内心では思いながら、表面上は感心してみせるようなものもあるかもしれない。また、昭和の頃に四畳半の部屋で暖房が炬燵ひとつだった生活には戻りたくないけれど、なぜか右肩上がりの美しい時代を話題に上せてしまうことと等価なものもあるにちがいない。
▼それだけを指摘しておけば、この映画の評価としては十分なのだが、いわば座興として、映画を観ながら浮かんだ私の個人的な連想を、以下に記してみる。まず、この作品には、男女一組の小学生が、給食時間に放送室で音楽をかけながら決まった台詞を読み上げるシーンがある。実は、私も小学生時代に放送係をしたことがある。もっとも、私の場合は、その係に任命される前に、学期の途中で私一人だけ、クラスを替えられていた。今ならば多動児と名づけられるだろうが(当時は問題児と呼ばれた)、私がしばしば担任だった女性教師の指示に従わなかったからだ。
▼しかし、新しい男性の担任は、クラス変更に際し、「高岡よ、わしは一度、お前の担任をしてみたかったんじゃ」と理由を説明した。そのとき私は「俺って、意外と教師に人気があるんだな」と勝手に誤解して「いいよ」と即答したが、今から振り返るとうまい説明を与えられたと感心する。そして、新しい学級では、他児から私を少しでも隔離する方法として、放送室で機材をつないで音楽を流す任務を与えられた。一方、この映画の学校(世田谷区立塚戸小学校というらしい)は、画面で観る限り、それなりの規模の学校のようだから、必ずや多動児や問題児が一定数いるはずだが、それらしき児童は登場しない。(放送室の男女も問題児にはおよそ見えない。)どこに隔離されているのだろうか。
▼次に、この作品には、掃除や給食の配膳を児童が行うことが、日本の教育の美点として描かれている。だが、私は小学校時代からずっと、うまく言葉に出来ないながら、それに違和感を懐いていた。今なら多少の反論を加えることも出来る。かなり前から、客に働かせて料金を巻き上げる店(マクドナルド方式)が、日本を含む各国を席捲してきた。現在、それはセルフレジという形で拡大している。しかし、どちらも客の労働に対価は支払われない。児童による配膳や掃除は労働ではない、生活指導だという反論に対しては、一昔前の劣悪な日本の精神病院では、同じ理屈で患者を働かせていたことを反証として挙げておけば十分だろう。
▼その他、コロナ禍の2021年に撮影されたというこの映画には、来たる東京五輪への言及がみられる。東京五輪といえば、森元首相の長いスピーチ中に、多くの選手が寝転んで談笑していた姿が印象的だった。学校では許されないだろうが、いい姿だと思った。